要介護者や高齢者が意識不明状態に陥った場合の緊急時対応
要介護者には高齢者が多いので、突然意識がもうろうとして倒れ込む場合があります。
この場合は、まず119番で救急車を呼ぶか医師になどに連絡することが最優先です。
次に意識が有るか無いかを確認し、安全を確保できる場所まで要介護者や高齢者を運び、呼吸をしていない場合は気道を確保して人工呼吸などを施します。
要介護高齢者などが意識を失う主な原因
主に次のようなことが要介護高齢者などが意識をなくす原因として挙げられます。
心臓疾患を抱えていたり、日常的に高血圧状態が続いている高齢者などは、脳血管障害(脳卒中)を発症していることが考えられます。
低血糖や糖尿病を患っている高齢者などの場合は、昏睡が原因で意識を失い倒れたりするケースもあります。
どちらにせよ、急に要介護高齢者などが倒れ込んだ場合、ホームヘルパーなどの介護職や家族介護者は、まず119番に電話をして救急車を呼んだり、かかりつけ医がいればすぐに連絡することが重要です。
意識有無の状態確認のポイント
- 高齢者の肩や腕を軽く叩く・ゆする、名前を耳元で呼ぶなどして、どのような意識状態かの確認を行います。
この時の注意点は、身体を激しくゆする、強く叩くなどの行為は絶対してはいけません。
- 次に腕や手を軽く摘まんでも全く反応しない時は危険な状態と言えます。
- 脈の有無を手首又は首を触って確認し、呼吸の有無も鼻先や口先に顔を近づけたり、胸の動きを見たりして確認します。
もし、脈や呼吸がないとわかった場合は、迅速に介護職員初任者研修などで習った心肺蘇生を施す必要があります。
- 顔色やくちびるの血色が悪くなっていないか、手足に異常がないかなど体全体を観察します。
- 訪問介護時に利用者が部屋で意識を失い到れている状態をホームヘルパーが発見した時は、倒れている周りの状態もしっかり観察しておく必要があります。
これは、倒れた症状の原因を調べる際に必要になることもあるためです。
意識がない場合の態勢保持と注意点
- 右半身を下にして寝かせると胃が下側になるため、吐きにくくなります。
- 呼吸できるよう気道を確保するため、一方のひざを曲げさせて、あごを片手で支えるような態勢にします。
- 気温が低い場合は、タオルケットなどで寒さを防ぎます。
以上のような態勢を図で表すと次のような状態になります。
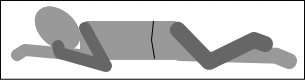
要介護者が倒れた場合は安全場所や気道の確保も重要
1. 安全場所の確保
要介護者が自宅の浴室や便所などで倒れた時は、居間など広い部屋に移動し、外出介助の際に倒れた場合は、安全な場所に運びます。
移動する場合は、できる限り頭部を動かさずに静かにゆっくりと移動しますが、自宅の場合はシーツや座ぶとんなどを使ってゆっくりと引きずるよう移動すると安全を確保しながら動かすことが出来ます。
2. 口の中をチェック
安全な場所や広い場所に移動できれば、まず□中をチェックします。
嘔吐していれば呼吸に支障がでるため、すぐに□の中に溜まっている嘔吐物を指でかき出し、顔は横にして寝かしておきます。
3. 気道の確保
しっかりと呼吸できるように気道の確保を行う場合は、次の点に注意します。
- 利用者の態勢を仰臥位(仰向け)の状態にします。
- 介護職は片手を利用者の首の下に差し込み少し持ち上げます。
- 持ち上げた状態で、もう一方の手を利用者の額に当て押し下げます。
- 但し楽だからと言って首下に枕を当ててはだめですし、身体の締め付け感が強い衣服は脱がすかチャックやボタンを外します。
介護職は普段から緊急時の備えをしておくことが必要
介護現場ではいろいろな緊急事態が発生しますが、実際に仕事場で直面すると、知識では分かっていても、緊張で気が焦ったり慌てたりして上手く対応できないことも少なくありません。
例えば糖尿病を患っている高齢者は低血糖が原因で昏睡状態に陥ることがありますが、この場合は砂糖水を与えるだけでも効果があります。
介護に携わっているホームヘルパーや介護職員は、常に自分が担当している利用者の心身状態を観察し、現状の体調や状況をしっかりと認識して、今後発生しそうな緊急事態に対しての対処法などの知識や手順を把握し、迅速に対応できるように備えておくことも必要です。
救急車を呼ぶ手順
- まず、119番に電話をします。
- 次に、「救急か火事のどちらですか?」とオペレーターから問われるので、「救急対応願います。」と答えます。
- さらに利用者の氏名、住所、倒れた場所までの道順や目印、状態を伝えます。
訪問介護先の利用者宅で緊急事態が起こった場合に備えて、ホームヘルパーは、利用者が倒れた時の状況を洩れなく伝えるために、日時、氏名、場所、状態、意識の有無、応急処置の実施内容など、伝達項目を用紙にまとめ、電話の近くに掲示しておくのも有効な手段です。







