歩行の介助法(自立度が高い場合)
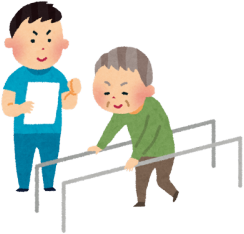
介助の視点
両手両足に麻痺などの障害がなく、単に加齢によって少しふらついたりしている高齢者の場合は、歩行補助具を使用する必要がない人がほとんどで、比較的自立度が高いと言えます。
但し、歩く場合に若干のふらつきがあるので、介護職員の見守りが必要となりますが、現状の歩行機能を維持し、活動範囲を狭めないような介助が必要です。
高齢者は、加齢や機能障害により次のような問題が起こるので、安心感を与えれるように下記の点に注意して介助を行います。
- 身体の重心が不安定なため転倒しやすいので重心線が支持基底面積よりはずれないようにする。
- 重心線は後方に移動しがちなので、前方に重心がかかるように姿勢を調節する。
- 太ももやすねの筋肉などが同調してうまく動かないので、足関節の可動性が衰えて足の蹴上げがうまく出来ずすり足歩行になり、段差が少しあってもつまずきやすくなります。
なので、足のつま先が下がったままになっていないか観察する必要があります。
歩行介助のポイント
平地歩行する際の介助ポイント
- 歩行介助の仕方を利用者に伝え同意・理解してもらいます。
- 利用者の少し後方に立ち、いつでも補助できるように身構えておきます。
- 立ち位置は、次の点に注意します。
- 利用者の利き足と反対側に立つ。
- 足の筋力の弱い側に立つ。
- 車道側に立つ。
- 足運び、膝のふらつき、障害物などに注意します。
- 利用者と会話をしながら、気分や体調が悪くないか観察します。
障害物や段差越えする際の介助ポイント
- 前方の障害物を利用者がまたぐ場合は、利用者の少し後方に立つようにします。
- 歩行バランスが崩れていないか安全性に配慮し、状況によっては足の運び方などを助言します。
- 障害物をまたぎ終わった後に、足に異常がないか体調に変化はないかなどを尋ねたりして確認します。
階段を昇り降りする際の介助ポイント
- 利用者には手すりを必ず使用して階段の昇り降りを行ってもらいます。
- 階段を上がる場合は、歩幅を広めに取りながら介護職員は利用者より1段下に段をまたいで立ち、バランスを突然崩し利用者が転落してこないように態勢をとります。
- 階段を下りる場合は、利用者より1段下に段をまたいで立ち見守ります。







