残存能力を把握し自立支援を行う
身体に拘縮や麻痺がある利用者は、ほとんどの場合、移動・移乗介助を必要としている方が多くいるので、介護職はその麻痺の程度に応じた介助を行えるよう検討する必要があります。
そのためには、麻痺の種類や関節の動きなどについての基本知識をしっかり理解しておくことが重要です。
麻痺の程度
| 麻痺の種類 |
原因
状態 |
| 四肢麻痺 (両側上下肢の麻痺) |
大脳、脳幹、頸髄などの障害が原因。
ほとんどの動作に介助が必要となり、体幹筋も麻痺するために座位の保持も困難。 |
| 対麻痺 (両側下肢の麻痺) |
脊髄損傷に起因する場合が多い。
動作のほとんどを健全な両側上肢で行える。 |
| 片麻痺 (片側上下肢の麻痺) |
頭部外傷、脳卒中などが原因で脊髄や脳の片側などに損傷を負った場合に起こる。
大抵の動作は自立しているが、重度の麻痺では、自力でバランスを保つ能力が衰え、介助が必要となるケースがある。 |
| 単麻痺 (四肢(両手両足)の内、一肢だけの麻痺) |
ほとんどがポリオなどの末梢神経の損傷が原因。
介助が必要でない場合が多く、基本的な動作は自立している。 |
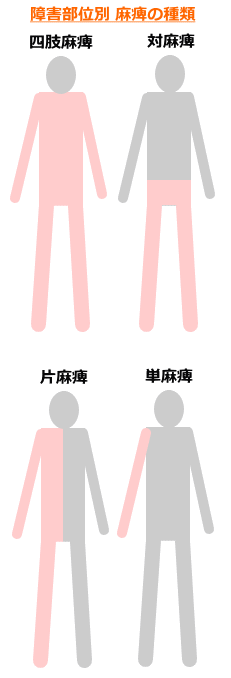
関節の可動域
人間には骨と関節がありますが、関節はいろいろな方向に動かすことが可能ですが、無理な動きをすると関節がはずれたり、最悪の場合、骨折することもあります。
関節には可動域があるので、一定の範囲しか動かすことができません。
次に、体の各部位と動きについて見ていきましょう。
| 関節部位 | 動き |
| 頸部 | 身体の中心軸を回したり、前後に傾ける動きなどが可能。 |
| 肩や肘 | 肩や肘の角度を広くする後方への動き、肩や肘の角度を狭める前方への動きなどが可能。 |
| 手や足 | 足は膝関節や足首を屈伸でき、手は曲げ伸ばしや捩じって回転させる動きなどが可能。 |
| 股関節 | 股関節は、まっすぐ立った状態から、屈曲・伸展・外転・内転・外旋・内旋などの動きが可能。 |
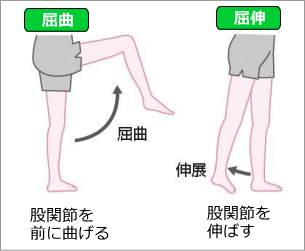
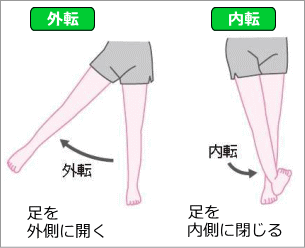
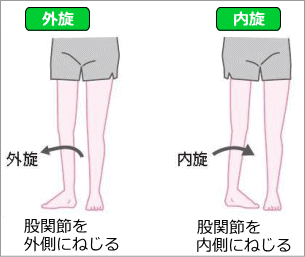
図引用元:
股関節はどんな関節でどの方向に動くのか?
股関節はどんな関節でどの方向に動くのか?
身体機能の残存能力を活用した介助
介護士は、利用者の麻痺の程度や関節可動域などを必ずチェックし、その程度に応じた介助の仕方を考えて移動・移乗の介護を行うようにします。
但し、介護士は自立支援という観点から介助を行うことも大切で、利用者が自分でできる行為は本人に行ってもらい、残された機能や能力を発揮できるよう配慮しながら介助を行うことが重要です。







