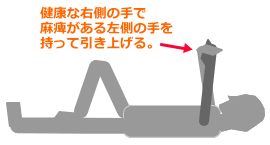片麻痺があっても全員が寝たきり状態になるわけではない
片麻痺と聞くと、ほとんどの人がどうすることもできないという印象を持っていて、寝たきりの状態をイメージする人も多いようですが、実際はよほどの事情がない限り、片麻痺の方が全員寝たきり状態になるようなことはありません。
寝たきり状態になる稀なケースは次のような時で、自分の意志で自発的に動けない場合です。
- 意識がない場合
- 意識はあるが広範囲に渡って脳障害がある場合
このようなケースに陥っていなけれは、手脚が麻痺により重い障害が起こっている状態であっても、寝返りがまったくできず寝たきり状態になることはありません。
寝たきり状態に陥らないようにするためには、寝返りをできるようにするということが第一歩になります。
まず、寝返りのしくみと体位変換の介助の基本のページで解説した「自然な寝返りのしくみ」を参考にして、片麻痺状態であっても、何ができて何ができないのかを確認してから具体的に介助の仕方を決めていくようにしましょう。
但し、介護職員や介助者は要介護者本人が自分でできることまで出しゃばって介助してはいけません。
介護者は、要介護者が自分でできる行為はじっと見守り、できない動作のみを介助して残存機能の衰えを防止し、可能な限り自立を促せるようにしていきます。
片麻痺状態の場合の動作チェック
片麻痺の場合は、次の3箇所についてどこまで動作ができるかどうかを確認していきます。
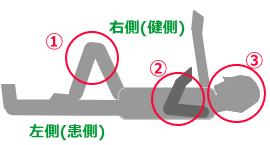
| 確認項目 | 内容 | |
| ① |
ひざは立てることができるか?
|
麻痺を起こしている脚はひざを立てることができても自然と倒れてしまいます。 利用者の中には麻痺していない反対側の健康な脚を使って強引に麻痺側の脚をすくい上げてひざを立てようとする方もいます。しかし、脚が麻痺している場合は鉄アレイの固まりのように重く感じ、無理すると腰まで痛めることになりかねません。 このような無理な動作を利用者がしていないか、介助者はよく注意する必要があります。 |
| ② |
腕は上げることができるか?
|
両腕を上げられるかどうかの状態も利用者により次のように様々です。
|
| ③ | 頭や肩を浮かすことはできるか? |
麻痺は一部の例外を除けば、通常首・お腹・背中の筋肉には起こりません。 脳卒中の場合も重篤なケース以外は、頭・肩を浮かして上げることは可能です。 |
寝返りする向きは?
寝返りを行う場合は、麻痺側とは反対方向に寝返りを行うようにします。
麻痺と反対側の動かせる腕の筋力をフル活用して寝返りを行うことで、少しでも筋力アップを図ります。
筋力が強くなれば体重を支えきることができ、寝返り状態から肩肘立ちができ、最終的に起き上がることができる状態まで持っていくことができます。
片麻痺の寝返り介助の手順
寝返りの準備姿勢をしっかりとれる場合
- 寝返りの準備姿勢をとってもらう
利用者には、まず、ひざを立て、手を上げ、頭や肩を浮かした姿勢をとってもらいます。 - ひざと手を軽くつかむ
次に、介護者は利用者のひざと手を軽く掴みます。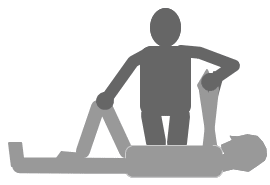
- ひざと手を手前にゆっくりと引く
介護者は掴んでいる利用者のひざと手を自分が立っている側にゆっくりと引いていきます。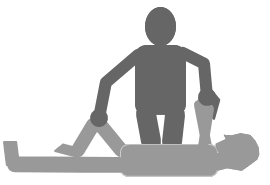
- 横向きになるまで引き続ける
介護者は要介護者の姿勢が横向きになるまで、しっかり状態を確認しながらゆっくりと自分が立っている側に引いていきます。横向きになり終えるまで途中で手を離さず軽く添えて誘導します。
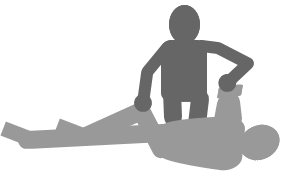
寝返りの準備姿勢をしっかりとれない場合の注意点
次のような寝返りの準備姿勢を十分にとれない時は、手前に引く際に掴む個所を変更します。
- 肩を上げることは出来ても膝を立てれない場合は、無理してひざを引いても腰を浮かすことはできません。
なので、腰をつかんで手前に引くように対処します。
- ひざを立てることが出来ても肩をしっかり上げられない場合は、手を掴んで無理に引くのではなく、ひざと肩をつかんで手前にゆっくりと引いて対処します。