介護職は食事介助の際、理想的な食事姿勢をチェックすること
介護職員初任者研修が修了し、食事介護を行う場合、利用者の食事姿勢が食べ物を飲み込みやすい理想的な姿勢になっているかを確認してから介助することが大切です。
誤嚥などを防ぎ飲み込みやすい理想的な姿勢は、床にピッタリかかとが着いた状態で前かがみの姿勢が最も理想的食事姿勢になります。
イスは腰深く座ることが可能な背もたれ付きであることと、利用者が前かがみの体勢で床に両足のかかとをぴったりと着けることができる高さのイスと、テーブルも高すぎないものを準備します。
それによって誤嚥などの心配なく安心して食事ができるので最も理にかなった食事姿勢といえます。
姿勢も安定し、食べ物を誤嚥する可能性もほとんどありません。
なお、片マヒなどを抱えている方は左右のバランスがとりにくいので、イスも肘当てがあるものを用意します。
介護用具による食事姿勢での悪い姿勢と良い姿勢の事例
介護ベッドでの食事姿勢
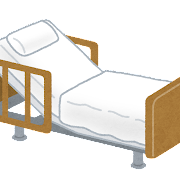
介護施設や病院などの医療機関で多く使用されているギャッジベッドですが、60度ほど起こした状態での寝た姿勢で食事を摂っている光景もよく見かけたりします。
嚥下障害を患っている方の衰えた飲み込む力を補助するには有効な一面もありますが、食事を摂るときには大変不自然な体勢であるのは間違いありません。
実際には、この状態での食事姿勢は食べ物を飲み込みにくくなり誤嚥を誘発しやすくなります。
顔が上向きになるので視線が斜め上になり食べ物が見えにくく、飲み物などを飲むときにこぼしやすくなります。
また、ベッドにもたれかかった状態にあるため肩や肩甲骨が圧迫され、腕を動かしにくくなりがちです。
最も問題なのは、食べ物・飲みが喉に自然に流入しやすくむせて誤嚥を誘発し、最悪の場合は肺炎・気管支炎を引き起こす要因になります。
 ベッドの端に座って床にかかとが密着するような高さにベッドを調節し、ベッド端から足を垂らして座る食事姿勢は大変理想的です。
ベッドサイドには座った際におへそ部分にテーブル位置がくるくらいの高さのテ-ブルを使用します。
安全で安定した姿勢を確保するには、両足ともかかとが床にしっかりと密着していることが重要です。
なので、かかとが浮いた状態にならないようにベッドの高さを適切に調節して使用するようにしたいものです。
ベッドの端に座って床にかかとが密着するような高さにベッドを調節し、ベッド端から足を垂らして座る食事姿勢は大変理想的です。
ベッドサイドには座った際におへそ部分にテーブル位置がくるくらいの高さのテ-ブルを使用します。
安全で安定した姿勢を確保するには、両足ともかかとが床にしっかりと密着していることが重要です。
なので、かかとが浮いた状態にならないようにベッドの高さを適切に調節して使用するようにしたいものです。
車イスでの食事姿勢

リクライニング式車イスで食事を摂るのは、まっすぐに起きた姿勢を保持できない次のような方のみに限定して使用するようにしましょう。
- イスや通常の車イスでは痛くて座れない方
- 長時間同じ姿勢を維持するのは苦しいという方
- 片麻痺などの障害でまっすぐに起きた姿勢をとれない方
あくまで、次善策という前提でリクライニング式車イスを利用し食事を摂るようにします。
ベッドで寝た状態で食事をするよりは、車イスなので足を下ろせるという観点ではましですが、可能な限り上半身を起こした状態を保てるように努力してください。
テーブルに好きな食べ物を発見し、思わず体を起こしたという方もいますので、何回も繰り返すうちに一般的な車イスに座ることができるようになる方もいます。

通常の車イスは食事を摂るのに適していますが、車イスは安定した姿勢で移動できるように背中側のシートは多少の傾斜を設けているため、前傾姿勢が取りにくい場合があります。
介護施設の中には、テーブルに車イスのひじ当てがぶち当たらないよう意図的にテーブルの高さを上げているケースも見られます。
但し、テーブルが高すぎると前傾姿勢になりにくく、すごく食べずらい姿勢になります。
もし、ひじ当てがテーブルにあたっても前かがみの姿勢になれば普通に食事を摂れるので、むしろテーブルの高さに注目し座高に合致したテーブルを使用することが大事です。







