調節機能がある車いすを重視して選ぶのがポイント
座れる、移動できるということが車イスの主な機能になりますが、車いすを選ぶ場合は、移乗のしやすさも重要な判断材料になります。
自力歩行が困難な利用者は、ベッドから車いすやポータブル便器へ乗り移ったりするケースが多くあります。
なので、車イスは、座りやすさ、移動のしやすさ、移乗のしやすさを検討して自分にあったものを選ぶようにします。
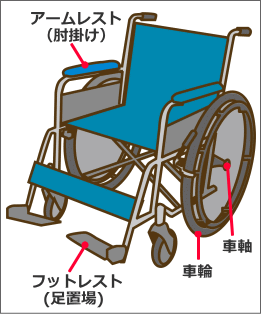
「座りやすさ」「移動のしやすさ」を確保する
車輪が取り外し可能で、車軸の位置を変更できるものが最適です。
車軸の高さを調整することにより、座面を自分にあった高さに調整でき安定した姿勢で座ることができます。
また自力で車輪を駆動させる場合、前側に車軸がある方がスムーズで楽に移動できます。
「移りやすさ」を確保する
アームレスト(肘掛け)がワンタッチで取り外しできるものが最適です。
ベッドからポータブルトイレなどへ乗り移る際にはポータブルトイレ側のアームレストを外せるので大変便利です。
特に全介助が必要な利用者の場合、アームレスト(肘掛け)の取り外しができないと移乗介助を行う際に大変な労力を要することになります。
フットレスト(足置場) の取り外しができることも大切です。
車いすとベッドや便器との間で移乗を行う場合、安全面から考えるとフットレストがあることにより、乗り移る時に脚が引っかかり事故を起こす可能性があるからです。
自分に合った車いすの調整の仕方
車いすを使用する場合は、次の点に注意して適正な調節を行い使用するようにしましょう。
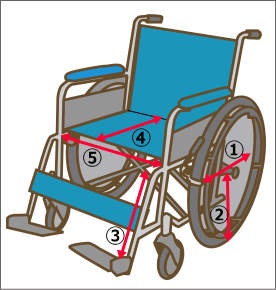
上図の①から⑤まで調整内容は、下記に解説しています。
① 前後に車軸の位置を変えて調節してみる
- 前側に車軸の位置をずらした場合:
自力での駆動がスムーズにできる - 後側に車軸の位置をずらした場合:
・安定性が増す
・車輪が前に出っ張らないので、アームレスト(肘掛け)を取り外しての介助がしやすくなります。
② 上下に車軸の位置を変えて調節してみる
車軸の位置を変えることで、床から座面までの高さを適切に調整でき、車いすとベッド・便座などの間の移乗がしやすくなります。
③ フットレスト(足置場) を適正な長さに調節する
長さが最適な場合フットレストの長さは下図のように膝裏と足裏がぴったり着くようにします。
こうすることで脚全体の体重を車いすで支えることができ脚は疲れません。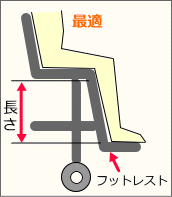
体重がお尻の坐骨に集中し痛くなります。
長すぎる場合足裏が着かずブラブラし座面の角に膝裏が当たって痛くなります。
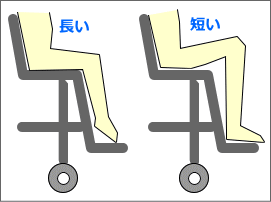
④ シート(座面)の奥行きを適正に調節する
車いすに座った時に奥行きが深すぎると、下図のように背中とイスの背もたれの間にすき間ができ、お尻が前にずり落ち猫背のような不安定な姿勢になります。
そんな場合は、隙間をクッションで埋めるように調節します。
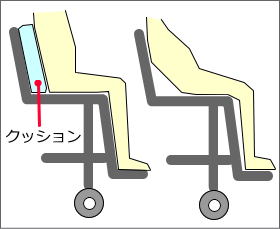
⑤ シート(座面)の幅は自分の体より広すぎないものを選ぶ
利用者の中には、障害などにより左右のバランスがどちらかに偏っている方もいます。
座面の幅が体の幅より広すぎる場合は姿勢が安定しないので、窮屈と感じない程度で自分の体形に合った車いすを選ぶようにします。







